岡豊城

岡豊城跡は、長宗我部氏の居城跡として知られる中世の城跡で、平成20年(2008)7月28日に国の史跡となりました。
長宗我部氏は鎌倉時代に地頭として土佐へ入国したと伝えられており、それ以後、長岡郡を中心に勢力を拡げ、戦国大 ...
郡上八幡城

郡上八幡城は、戦国時代末期の1559年(永禄2)、奥美濃の戦国武将遠藤盛数が八幡山に砦を築いたのがはじまりです。
遠藤氏はもともと美濃の名族東氏の支流であったが、本家の東氏を滅亡に追い込み、郡上八幡一体を手に入れた。
越前大野城

越前大野城跡は、大野盆地の西側に位置する標高約250mの亀山と、その東側に縄張りを持つ平山城跡です。織田信長の武将、金森長近により天正年間(1573-1593)の前半に築城されました。越前大野城は亀山を利用し、外堀・内掘をめぐらし ...
志布志城
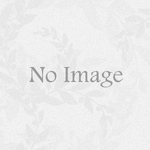
築城年は不明で1026年頃には山城としての形態は整えられ、南北朝期から戦国期に拡大強化されたものと考えられる。1615年の一国一城令により廃城となった。内城を中心に、松尾城・高城・新城の4城からなり、総称として志布志城という。本丸 ...
八代城
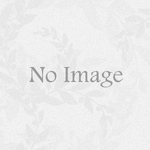
八代城は、元和5年(1619)の地震により麦島城が崩壊したため、熊本城主加藤忠広が、幕府の許可を得て加藤正方に命じ、同6~8年に掛けて球磨川河口北側の松江村に築城した平城です。寛永9年(1632)加藤氏の改易により熊本城主となった ...
田丸城

野面積みの石垣が美しい南北朝時代の城址。
北畠親房・顕信父子が玉丸山に城塞を築き、南朝の拠点としたと伝えられます。
天正3年(1575)織田信雄により平山城の田丸城が築かれその後稲葉氏、藤堂氏、久野氏と城主が変わり ...
赤木城
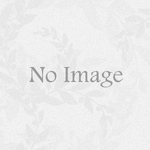
藤堂高虎によって天正17(1589)年頃、反対勢力を抑える目的で築城されたと言われ、主郭を中心とした三方の尾根上と裾部に郭を設けています。尾根を利用した郭配置は中世山城の様相を引き継ぐ一方で、高く積まれた石垣や発達した虎口など近世 ...
原城

原城は 日野江城の支城として有馬貴純により築かれた。有馬氏が転封後、代わって領主となった松倉重政は、不便な日野江城から島原へ移り、廃城とったと同時に原城も廃城となった。
寛永14年(1637)に勃発した島原の乱では一揆軍 ...
小牧山城

小牧山城は織田信長が初めて新築したお城です。
1563年、平城であった清洲城が、水害に見舞われることも多かったので、信長は小牧山へお城を築き居城を移したようです。しかし、僅か4年で岐阜城に居城を移したため、小牧山城は廃城に ...
佐伯城

佐伯城は慶長5年(1600)の関ヶ原の戦い後に、新たに築かれた唯一の山城である。
近世になっても大和高取城、美濃岩村城、備中松山城などの山城が存在するが、それらは戦国時代より継続した山城であった。城は、豊後水道を望む標高1 ...