福知山城

福知山城は、 天正8年(1580) ごろ、丹波平定に成功した明智光秀が丹波の拠点として新たに城を築いたのが始まりとされています。
以来、 戦乱の時代、城主が交代する中、順次整備が進められ、慶長5年(1600) ごろに完成し ...
唐津城

唐津城は豊臣秀吉の家臣、寺沢志摩守広高が慶長七年(1602年)から7か年の歳月を費やして完成した。築城には名護屋城の解体資材を用いたと伝えられ、城を要にした砂浜が翼を拡げた鶴のようにも見えることから、別名『舞鶴城』とも呼ばれている ...
津城

津城は、織田信長の弟信包(のぶかね)によって築城された。信包は信長が伊勢へ勢力を伸ばしてきたとき、長野氏の養子に入ったものである。天正8年(1580)には五層の天守閣が完成し、当時柳山付近が中心であった津の町から町家や寺院が移され ...
福井城

福井城は慶長6年~11年(1601~06)に徳川家康の次男、結城秀康によって築城されました。秀康時代の福井城の建物は寛文9年(1669)に焼失してしまいました。藩の権威を象徴していたのが本丸の北西隅に聳えていた天守で、高さ約30m ...
引田城
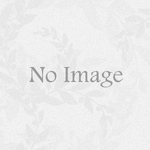
引田城は、東かがわ市引田の北側に岬状に突き出した城山(標高82m)の山頂に築かれています。江戸時代編修の軍記物語『南海通記』にある応仁年間(1467~69)に寒川氏が領したとあります。戦国時代には阿波三好氏との攻防があり、引田城の ...
近江八幡山城

豊臣秀吉、秀次により築かれ秀次の居城でもあった。建材として安土城の石垣が使用された。
データ所在地滋賀県近江八幡市宮内町築城年天正13年(1585)別名八幡城、近江八幡城形態連郭式山城天守構造不明主な城主豊臣秀次、京極高次主 ...能島城

能島城は、フロイスの記録にも登場する能島村上水軍の根拠地と知られ、周囲約820mの小島を、3段に削って平らにして曲輪とする海城で、土塁や堀などはみられない。能島村上水軍は、村上武吉の代に、毛利氏支配下の水軍として活躍し、1576年 ...
岸和田城

大阪湾に臨む微高池に築かれた平城である。現在は海岸線から離れているが、かつて外郭の一部は海浜に面して築かれていた。本丸付近は一部地盤が軟弱であったためか石垣裾に犬走を設けている。
データ所在地大阪府岸和田市岸城町9-1築城年 ...備中高松城

当城は三村氏家臣石川氏により築かれたとされている。1582年織田家臣羽柴秀吉による中国攻めにより清水宗治は出家した兄の月清らとともに水上で切腹した。その後宇喜多氏の家老花房氏が入城。現在本丸以外は水田や住宅地となり、本丸跡に宗治の ...
郡山城

1585年豊臣秀吉の弟秀長が大和国・和泉国・紀伊国三ヵ国100万石余の領主として郡山城に入る。秀長は城を100万石の居城に相応しい大規模なものに、また大阪城を守る東の備えの城とすべく大改修と城下の整備を行った。
データ所在地 ...