根室半島チャシ跡群

チャシは砦や柵囲いを意味するアイヌ語である。丘陵や海岸に面した断崖上に自然地形を生かして堀、土塁、盛土で形成された単純構造のものが多い。戦いのための城砦だけでなく、祭祀、集会、見張り場として利用されたようである。-日本100名城へ ...
弘前城

津軽を平定した津軽為信の子信枚が築城。本丸を二の丸以下の曲輪が囲むように縄張された輪郭式の城である。本丸だけが石垣造りでその他の曲輪は土塁で造られた。本丸には馬出が残っている。築城時の天守は五重だったが、落雷により焼失。江戸時代後 ...
根城
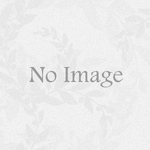
根城は、建武元年(1334年)に南部師行(なんぶもろゆき)により築城された城です。
寛永4年(1627年)に領地替えにより使われなくなるまでの約300年間、八戸地方の中心でした。主殿と呼ばれる当主が儀式を執り行った建物を中 ...
盛岡城
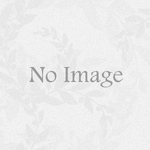
盛岡城は岩手県盛岡市にあった日本の城である。国の史跡に指定されている。別名は不来方城であると一般に理解されているが、厳密には盛岡城の前身であり両者は別の城郭である。Wikipedia
データ所在地 岩手県盛岡市内丸1-37築 ...久保田城
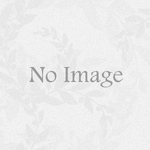
久保田城は、慶長七年(1602)に出羽国へ国替えとなった佐竹氏二十万五千八百石の居城である。特徴は石垣がほとんどなく、堀と土塁を巡らした城であることと、天守閣をはじめから造らなかったことが挙げられる。
データ所在地 秋田県秋 ...松前城

福山城(松前城)は松前町福山の台地に築かれた平山城で、近世に築城された北海道唯一の城郭である。
松前家五世慶広が、天正17年(1589)徳山(大館)の居館焼失を機に、慶長5年(1600)福山の地で築城に着手し、同11年(1 ...
多賀城

多賀城は奈良時代に陸奥国の国府および、鎮守府(※1)が置かれた律令国家(※2)の行政、軍事の拠点である。約900m四方に築地がめぐり、中央に重要な政務儀式をおこなう政庁があった。
その周囲には行政実務を担う役所や兵舎、工房 ...
仙台城

仙台城は、初代仙台藩主伊達正宗によって造営され、慶長7年(1602)には一応の完成をみたとされています。
城は、東と南が広瀬川と竜の口渓谷の断崖、西が険しい山に囲まれた天然の要害で、石垣は主に本丸の周りに築かれました。
小峰城

奥州関門の名城と謳われた小峰城は、結城親朝が興国・正平年間(1340~1369)に小峰ヶ岡に城を構えたのがはじまりで、寛永9年(1632)に江戸時代の初代藩主、丹羽長重が4年の歳月を費やして完成させた梯郭式の平山城です。
二本松城

二本松城は、15世紀前半畠山氏の居城として築城されたといわれています。
その後、伊達、上杉、松下、加藤と城主がかわり、寛永20年(1643)に丹羽光重が二本松藩10万700石で入城し、以後、丹羽氏の居城として明治維新を迎え ...